

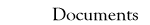
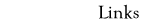
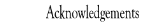


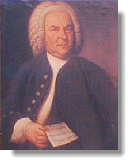
|
J. S. バッハ
ゴルトベルク変奏曲 BWV988
 楽曲解説
楽曲解説
この曲は、ヨハン・セバスティアン・バッハ(1685〜1750)によって1741年〜42年頃作曲された。
一般的な曲名になっている<ゴルトベルク変奏曲 Goldberg-Variationen >という曲名は
バッハ自身が付けたものではない。
この通称は没後52年の1802年に出版されたフォルケルのバッハ評伝に由来している。
バッハは『2段鍵盤をもつクラヴィチェンバロのための、アリアと種々の変奏』と称していた。
その後、バッハはこの曲を
『クラヴィーア練習曲集(第4巻) Vierter Teil der Clavier-Übung』
と題して1742年にニュルンベルクのバルタザール・シュミット社から出版した。
その表紙には、
『クラヴィーア練習曲・種々の変奏を伴うアリアから成る
〜2段鍵盤のクラヴィチェンバロ用〜愛好家の心の慰めのために 〜J.S.バッハによる』
と記述されていた。実際には、第4巻という表記はなし。
★フォルケルのバッハ評伝
ヨハン・ニコラウス・フォルケル(1749〜1818)は初めてバッハの評伝を書き表わした人物である。
その評伝の中の<ゴルトベルク変奏曲>の記述の引用から、この曲の成立背景がよく判る。
われわれはこの作品について、ザクセン宮廷の前任のロシア大使カイザーリング伯爵に多くを負っている。
伯爵はたびたびライプツィヒに滞在し、ゴルトベルクをバッハに紹介して、その弟子とした。
伯爵はたえず不眠に悩まされていた。
伯爵邸に逗留していたゴルトベルクは、そうした折には夜を伯爵の控えの間で過ごし、
眠れぬ主人のために演奏したのだった。
ある日伯爵はバッハに、そうした眠れぬ夜に彼を元気づける優しく生きいきとした性格のチェンバロ曲を、
ゴルトベルクのために作曲して欲しいと伝えた。
バッハはその望みには変奏曲集がふさわしいと考えた。
バッハはそれまで変奏曲について、和声的な構成がつねに繰り返されることから、
やり甲斐のない仕事だと考えていた。曲が完成すると伯爵はこれを<自分の>変奏曲と呼んだ。
眠れぬ夜には『ゴルトベルク、私の変奏曲のどれか一つを弾いてくれ』と言うのだった。
・・・・バッハは恐らく自作に対して、この時ほど大きな報酬を得たことはなかったであろう。
伯爵はルイ金貨が100枚つまった金杯をバッハに贈ったのである。
( Johann Nikolaus Forkel=フォルケル『バッハ評伝』より)
ただし、時代考証からこの時ゴルトベルクは14歳より以前であり、
バッハがそんな年少者にこれほど高度な曲を書いたはずはないとして、
また、それほどの報酬を得たにもかかわらず、献呈についての記述が一切ないことを理由に
フォルケルの記述を疑問視する声もある。新全集版序文ヴォルフの推論が興味深い。
|
 楽曲構成 〜ゴルトベルク変奏曲としての〜
楽曲構成 〜ゴルトベルク変奏曲としての〜
この曲は、主題であるアリアと30の種々の変奏曲から成っている。
主題であるアリアは、1725年の『アンナ・マグダレーナ・バッハのための音楽帳』の中の
<サラバンド>(第26番 BWV.988/1)としてすでに作曲されていたものが使われている。
(この説は現在逆となり、
ゴルトベルク変奏曲完成後に音楽帳に筆写されたことが確実視されている。)
このサラバンドにはたくさんの装飾音が使われているので、
一見変奏曲の主題としては難しそうに見えるが、実際にはこのメロディではなくバスが
変奏曲の主題の基礎として使われているのである。
主題は32小節のバス・パートを基本として変奏される。
そして、全体を通しての曲構成が32楽曲であるということも、この32の小節数を符合する。
また、主題のバス声部の「音」の数32に符合する。
つまり、基礎となる和音を1単位=全音符1拍としてバスを示すと、
8個ずつで1ブロックを形成し、全体は8単位×4ブロック=32単位で構成される。
ほとんどの変奏は1単位=1小節なので全32小節から成っているが、
第3、9、21、30変奏は1単位が2分の1小節なので、半分の16小節。
唯一の例外は第16変奏だけで、47小節となっている。
このバス主題がそれぞれの曲の根底を貫いているのである。
そして、もっとも明快な構成はこの「アリア」に始まり、
30の変奏を展開し、最後にふたたび「アリア」が現われ曲を終えること。
グレン・グールドがこの曲でデビューし、この曲で人生を閉じたように・・・・
(ちょっと無理あり?(^^;) )
ふたたび演奏されるアリアを暗示するかのように、
第30変奏にクォドリベットの『長いこと君に会わなかったね』が置かれているのも
粋な演出である。
あるいは、アリアの再現は延々のループを暗示しているのかもしれない。
この曲は第16変奏のフランス(風)序曲で後半が幕開けするような二部構成にもなっている。
この二部の対比では、前半よりも後半の方に2段鍵盤使用の指示が多く、
第30変奏に向かって響きは厚くなり、最後に穏やかな冒頭のアリアで曲をしめくくっている。
三部構成を意識した配置もある。
それは第16変奏のフランス(風)序曲から前後に等しく6つめの第10変奏と第22変奏に
フガートを配したことから推測することができる。
また、それぞれの変奏曲は3つずつのグループに分けることが出来る。
1つのカノンとひとつの2段鍵盤用の(イタリア的手法による)技巧的なブリラントな曲。
その間にはさまれた自由な性格的変奏曲で構成される。
変奏3曲ごとに配置されるカノンは、変奏を追うごとに同度から9度と音程間隔を拡げて行き、
その都度異なった音程から出発するように配置されている。
それは、「すべての可能な音程間隔によるカノンを、
最小の音程間隔から最大のそれへと高めて配置するという系統的な秩序をもっている」
( J.E.Dähler)。これらカノンが曲の主軸となっている。
また、カノン1曲ごとに、奇数拍子と偶数拍子が交替しており、
これは厳格なスタイルにおける性格の変化に役立ち、
またテンポの変化、対照に決定的な力をもっている。
<ゴルトベルク変奏曲>のカノンの考察については、Georg-Albrecht Eckleの解説
(同CDのライナーに掲載)に興味深いものがあるので機会があれば参照されたし。
いずれにしても、この<ゴルトベルク変奏曲>は緻密に構成された、
驚くべき曲なのである!
|

 楽曲構成 〜アリア・種々の変奏それぞれの〜
楽曲構成 〜アリア・種々の変奏それぞれの〜
さまざまな楽曲解説をもとにまとめたもの。
それぞれの変奏にある表題は、
デーラーとその師ノイマイヤーが演奏鑑賞の指針になるようにつけたもの。
ちょっとユニークなので付記しておいた。
 アリア - Aria
アリア - Aria
- オープニングのアリアは『アンナ・マグダレーナ・バッハのための音楽帳』の中に収められた
1曲<サラバンド>から。
 第1変奏 - Variation 01.(ポロネーズ)
第1変奏 - Variation 01.(ポロネーズ)
- 3/4拍子。クーラント風の2声のインヴェンション。
コンチェルト・グロッソ風。1段鍵盤。
 第2変奏 - Variation 02.(粋な会話)
第2変奏 - Variation 02.(粋な会話)
- 2/4拍子。トリオ・ソナタの形式による3声のシンフォニア。
独奏風:2つのヴァイオリンと通奏低音。2段鍵盤。
 第3変奏 - Variation 03.(ふたりの羊飼い)
第3変奏 - Variation 03.(ふたりの羊飼い)
- 12/8拍子。Canone all Unisono。自由なバスをもつ2声の同度(1度)のカノン。
上声部が1小節遅れ。1段鍵盤。
 第4変奏 - Variation 04.(羊飼いの踊り〜パスピエ)
第4変奏 - Variation 04.(羊飼いの踊り〜パスピエ)
- 3/8拍子。パスピエ、トゥッティ風で<跳躍舞曲>を思わせる4声の模倣的な音楽。
1段鍵盤。
 第5変奏 - Variation 05.(吟遊詩人〜スカルラッティ風に)
第5変奏 - Variation 05.(吟遊詩人〜スカルラッティ風に)
- 3/4拍子。両手(声部)の交差をもつ2声のインヴェンション。
1段または2段鍵盤。
 第6変奏 - Variation 06.(魔法の鎖)
第6変奏 - Variation 06.(魔法の鎖)
- 3/8拍子。Canone alla Seconda 。自由なバスを伴う2声の2度のカノン。
上声部が1小節遅れ。1段鍵盤。
 第7変奏 - Variation 07.(楽しげに)
第7変奏 - Variation 07.(楽しげに)
- 6/8拍子。2声のジーグまたはシチリアーノ。独奏風。1段または2段鍵盤。
 第8変奏 - Variation 08.(波)
第8変奏 - Variation 08.(波)
- 3/4拍子。自由な性格的変奏、サルタレロ。
両手の交差をもつ2声のトッカータ風のインヴェンション。2段鍵盤。
 第9変奏 - Variation 09.(天使)
第9変奏 - Variation 09.(天使)
- 4/4拍子。Canone alla Terza 。自由なバスを伴う2声の3度のカノン。
上声部が1小節遅れ。1段鍵盤。
 第10変奏 - Variation 10.(城を守る小さな兵隊)
第10変奏 - Variation 10.(城を守る小さな兵隊)
- 2/2拍子。自由な性格的変奏、4声のトゥイッティ風フゲッタ。1段鍵盤。
 第11変奏 - Variation 11.(蝶々)
第11変奏 - Variation 11.(蝶々)
- 12/16拍子。両手の交差をもつ2声のジーグあるいはトッカータ風の音楽。
2段鍵盤。
 第12変奏 - Variation 12.(ナルシス)
第12変奏 - Variation 12.(ナルシス)
- 3/4拍子。Canone alla Quarta。
自由なバスを伴い対照的な動きでの2声の4度の反行カノン。
上声部が反行形で1小節遅れ。
1段鍵盤(ただし、バッハによる指定は欠落)。
 第13変奏 - Variation 13.(セレナーデ)
第13変奏 - Variation 13.(セレナーデ)
- 3/4拍子。自由な性格的変奏、カンティレーナ。独奏風。
2声のバス上に展開される装飾されたアリア。
フルートと通奏低音。2段鍵盤。
 第14変奏 - Variation 14.(朝の目覚め)
第14変奏 - Variation 14.(朝の目覚め)
- 3/4拍子。両手の交差と名人技的な技巧を伴う協奏曲風の音楽。
2声。2段鍵盤。
 第15変奏 - Variation 15.(眠りは死の鏡)
第15変奏 - Variation 15.(眠りは死の鏡)
- 2/4拍子。Canane alla Quinta 。ト短調、アンダンテ。
自由なバスを伴い対照的な動きをもつ2声、5度の反行カノン。
上声部が反行形で1小節遅れ。1段鍵盤。
 第16変奏 - Variation 16.(フランス序曲)
第16変奏 - Variation 16.(フランス序曲)
- 2/2および 3/8拍子。壮大なフランス(風)序曲。
自由な性格的変奏。トゥッティ風。1段鍵盤。
 第17変奏 - Variation 17.(オルガン)
第17変奏 - Variation 17.(オルガン)
- 3/4拍子。変奏14と類似した2声の協奏曲風の楽章。2段鍵盤。
 第18変奏 - Variation 18.(優雅さ)
第18変奏 - Variation 18.(優雅さ)
- 2/2拍子。Canone alla Sesta。
自由なバスがストレットに参加するアラ・ブレーヴェでの2声の6度のカノン。
ブレー風。上声部が半小節遅れ。1段鍵盤。
 第19変奏 - Variation 19.(こびとの踊り)
第19変奏 - Variation 19.(こびとの踊り)
- 3/8拍子。自由な性格的変奏、バルカローレ。3声のメヌエット、またはレントラー。
1段鍵盤。
 第20変奏 - Variation 20.(清純な娘)
第20変奏 - Variation 20.(清純な娘)
- 3/4拍子。
両手の交差、名人技的な技巧と弱拍に16分音符の動きをもつ2声の協奏曲風の音楽。
2段鍵盤。
 第21変奏 - Variation 21.(嘆き)
第21変奏 - Variation 21.(嘆き)
- 4/4拍子。Canone alla Settima 。
ト短調。自由な半音階的バスを伴う2声の7度のカノン。
上声部が半小節遅れ。1段鍵盤(ただし、バッハによる指定は欠落)。
 第22変奏 - Variation 22.(荘重さ)
第22変奏 - Variation 22.(荘重さ)
- 2/2拍子。
リチェルカール様式の自由なバスを伴う4声、アラ・ブレーヴェでの3声のフガート。
自由な性格的変奏。1段鍵盤。
 第23変奏 - Variation 23.(パンタロンとコロンビーヌ)
第23変奏 - Variation 23.(パンタロンとコロンビーヌ)
- 3/4拍子。
名人技的な技巧と走句で弱拍上の和声と両手の交差を伴う2声の協奏曲風楽章。
2段鍵盤。
 第24変奏 - Variation 24.(羊飼いの子守歌)
第24変奏 - Variation 24.(羊飼いの子守歌)
- 9/8拍子。Canone alla Ottava。
自由なバスを伴うジーグ風の2声のオクターヴのカノン。
シチリアーノ、パストラーレ風。上声部が2小節遅れ。1段鍵盤。
 第25変奏 - Variation 25.(ミゼレーレ)
第25変奏 - Variation 25.(ミゼレーレ)
- 3/4拍子。ト短調の自由な性格的変奏、アダージョ。
2声の半音階的なバス上の展開される装飾されたアリア。
独奏風。ヴァイオリンと通奏低音。2段鍵盤。
 第26変奏 - Variation 26.(王のサラバンド)
第26変奏 - Variation 26.(王のサラバンド)
- 3/4および 18/16拍子。3声。
上声に装飾されたアリアを置き、下声に 18/16拍子の流れるような声部をもった
3/4拍子のコラール・サラバンド。その機能は両手に交替される。2段鍵盤。
 第27変奏 - Variation 27.(上品な機智)
第27変奏 - Variation 27.(上品な機智)
- 6/8拍子。Canone alla Nona。
2声の9度のカノン。ギーガ風。
2声部が1小節遅れ。この曲だけ自由対位法によるバス声部がない。1段鍵盤。
 第28変奏 - Variation 28.(泉)
第28変奏 - Variation 28.(泉)
- 3/4拍子。トリル変奏。自由な書法での名人技的な協奏曲風の楽章。
トリルや二重トリルを多くもつ練習曲風の音楽。2段鍵盤。
 第29変奏 - Variation 29.(滝)
第29変奏 - Variation 29.(滝)
- 3/4拍子。弱拍上に和音をもつ同じく練習曲風の楽章。
トッカータ風。1段または2段鍵盤。
 第30変奏 - Variation 30.
(長いこと君に会わなかったね・キャベツとかぶらが私を追い出した)
第30変奏 - Variation 30.
(長いこと君に会わなかったね・キャベツとかぶらが私を追い出した)
- 4/4拍子。4声。自由なバスを伴う3声のクォドリベット。1段鍵盤。
クォドリベトとは、バッハの時代に数人で合唱する形式で、
それぞれが気ままに好みの歌を歌い重ねるもの。
ここでは『長いこと君に会わなかったね』と『キャベツとかぶらが私を追い出した』という
2つの俗謡が主題のバス声部と複合されている。
 アリア (ダ・カーポ)- Aria reprise
アリア (ダ・カーポ)- Aria reprise
- アリアの反復。
|

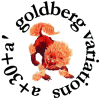 Last Update : May.05.1999
Last Update : May.05.1999
|
|